代表の稲田礼子です。
本コラムは、私が日頃の産業医活動の中で行なっている講話から、一部をご紹介するものです。健康経営※に取り組む皆様のお役に立ちますと幸いです。
今回は、秋の健康診断に向けて、第4弾「肝機能」についてのお話です。
目次
1.肝機能について
肝臓は「沈黙の臓器」と言われ、少々の障害では症状が起きません。
障害が進行しても自覚症状が出づらいため、異変に気が付いたときには時すでに遅し…というケースも。
2.肝臓悪化の流れ
肝臓の状態は、以下のような流れで悪化していきます。

①健康な肝臓
多少の障害に対しても、再生機能が働く。

②脂肪肝
肝細胞の30%以上に脂肪が溜まった状態。
メタボの合併も多く、放置すると肝炎に繋がる。初期段階では症状が現れず、気づきにくい。
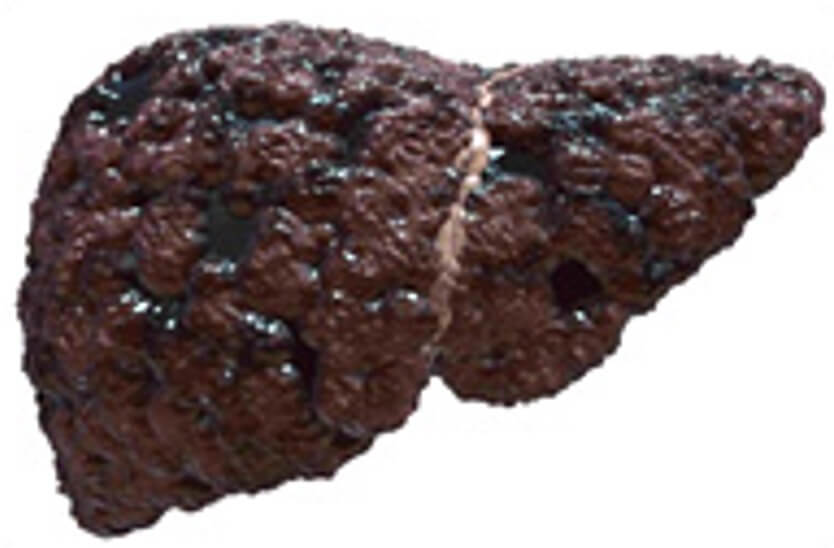
③肝硬変
肝臓病の最終段階。硬く小さく萎縮した状態。
吐血や腹水、黄疸といった症状が顕著に表れる。
ガン発生とも密接な関係。
3.健康診断で自分の肝機能をチェックしよう
健康診断でわかる肝機能の指標は下の3つです。
①AST(GOT)基準値 30以下
②ALT(GPT)基準値 30以下
③γ –GTP 基準値 男性 50以下 女性 30以下
4.肝臓病の予防・改善策
肝臓病の原因は主にウィルス、アルコール、肥満です。
生活習慣が原因の場合、肝臓病予防・改善には「食事」「運動」「飲酒」の見直しが有効とされています。
お酒を飲む人は、1日の量はほどほどに(缶ビールであれば1日500mlまで)、休肝日を設けましょう。
※健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
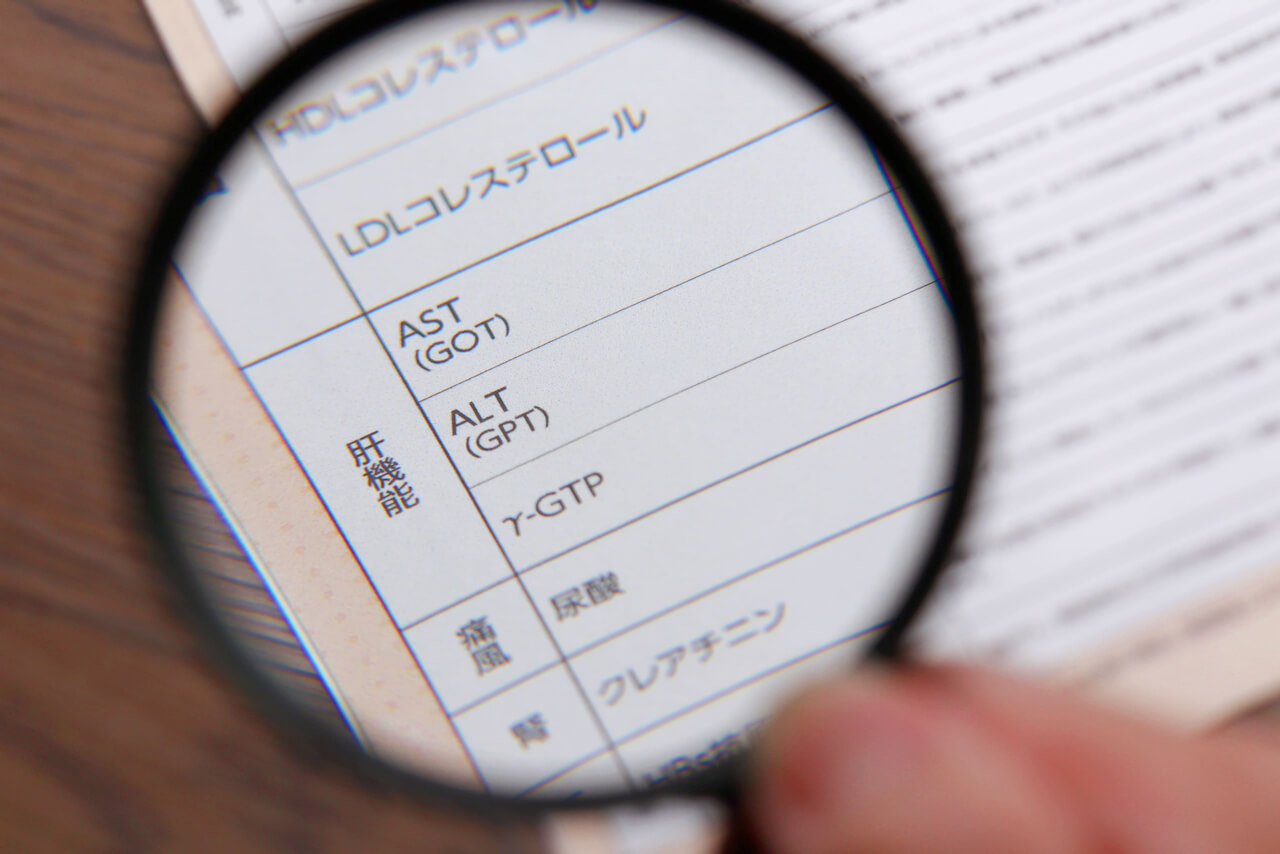








コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 関連する以前の記事はこちら秋の健康診断に向けて 第4弾「肝機能」(産業衛生講話シリーズ) […]